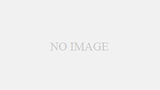俳文学会東京研究例会:第480回
日時:7月26日(土)午後2時30分~午後5時
場所:江東区芭蕉記念館会議室
【テーマ研究】
○鹿島美里氏「蔦屋重三郎のネットワークと江戸座俳諧―吉原から蘭学まで」
蔦屋重三郎が大河ドラマで取り上げられたことにより、江戸の出版や江戸戯作文学、吉原遊里に注目が集まっている。そこで蔦屋重三郎のネットワークから江戸座俳諧の俳諧交流によってもたらされた蘭学者や吉原者をはじめとする人脈・文化との繋がりについて考察していきたい。蔦屋重三郎は天明狂歌で知られているが、彼は吉原仲の町茶屋主人たちや大名子弟とともに江戸座俳諧にも参加しており、この俳諧交友がもとになり文化が生み出されていくこととなる。その文化圏に秋田藩士の朋誠堂喜三二や喜三二の秋田藩上司の佐藤晩得、駿河小島藩士の恋川春町、戯作者の山東京伝、蘭学者・戯作者の森島中良やその兄の桂川甫周がおり、蘭学や天文学の西洋の最新知識が戯作に取り入れられていった。さらに戯作の登場人物の顔は実在の人物の似顔絵をモデルにしていることも多く見られる。このうち朋誠堂喜三二は月成と称して俳諧を行っており、喜三二の俳諧の師亀成との係わりや、其角・春来と続く江戸座俳諧の系譜を読み解いてゆく。加えて吉原文化圏にいた大名子弟の松前文京と吉原仲の町茶屋長崎屋との繋がりや同じく大名子弟の松平雪川・未白の俳諧活動についても触れていきたい。
○近衞典子氏「浪華俳諧を考える―秋成の俳諧を中心に―」
上田秋成は小説作家、国学者、歌人として著名であるが、数多くの俳諧作品も残している。若い頃に俳諧に親しんだ秋成は、後年俳諧から離れていったと考えられているが、今回与えられたテーマは「安永・天明期の俳諧」であり、この時期を出発点として、改めて秋成と俳諧との関わりについて考えてみたい。
安永・天明期の秋成の俳諧活動と言えば、初めての宗因句集として評価される『むかし口』(安永六年刊)と、安永三年蕪村序、天明七年刊行の初の俳諧文法書『也哉鈔』に指を折るであろう。そして、この二書が誕生する土台には、中村幸彦により「宝暦・明和の大阪騒壇」と名付けられた時代と場所があった。具体的に秋成の俳諧作品や小説『癇癖談』、紀行『去年の枝折』等に触れつつ、秋成の芭蕉観、大坂城落城への関心、大坂における『連歌提要』享受、小説と俳諧との距離など、秋成俳諧および大坂俳壇の様相について考察したい。